DX への取り組みを加速するため、2019 年に Azure の IaaS によるクラウド リフトを開始した明治安田生命保険相互会社。2023 年 5 月には「クラウド ネイティブ」ベースのコンテナ環境での開発とデプロイを推進しつつあります。その基盤として採用されたのが、Azure Red Hat OpenShift。この他にも複数の PaaS が利用されており、Azure DevOps Services を活用した CI/CD パイプラインも実装されています。これによってリソース払い出しとデプロイをセルフ サービス化すると共に、アプリケーションのマイクロサービス化を推進、開発生産性とデプロイ スピードを高めつつあります。今後はこの基盤の上に、Azure OpenAI Service による生成 AI プラットフォームも構築する予定。また、GitHub Copilot の活用による、さらなる開発生産性向上も視野に入っています。


クラウド リフトだけでは限界があった開発スピードと柔軟性の向上
明治安田生命保険相互会社 (以下、明治安田) は、「明治生命」と「安田生命」が 2004 年 1 月に合併して誕生した、約 140 年の長い歴史と伝統を持つ生命保険会社。2017 年には新たな企業理念「明治安田フィロソフィー」を定め、お客様に「確かな安心を、いつまでも」お届けすると共に、「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」となることを掲げています。2024 年 4 月からスタートする「MY Mutual Way Ⅱ期」では、「生命保険会社の役割を超える」ことをめざしていきます。この言葉には、従来の生命保険会社の役割を大切にしながら、「ヘルスケア・QOL の向上」と「地域活性化」という二つの方向にさらに役割を拡充していく、という強い想いが込められています。これらを加速するための「DX 戦略」も積極的に推進しています。
その一環として現在進められているのが、システム インフラとアプリケーションのクラウド ネイティブ化です。Azure Red Hat OpenShift を中核に Azure 上でコンテナ基盤を構築、アプリケーションのマイクロサービス化に取り組んでいるのです。ここに至るまでの経緯について、明治安田生命 情報システム部 システム基盤開発室 システム基盤開発グループでグループマネージャーを務める石原 尚 氏は、次のように説明します。
「2014 年に十分に安定したプライベート クラウド環境を構築しており現在もそれを利用していますが、アプリケーション提供の機動性を高めるにはパブリック クラウドの活用が不可欠だと考え、2019 年に Azure の IaaS を採用したパブリック クラウド基盤を整備しました。これも高い安定性を実現していますが、IaaS へのクラウド リフトだけでは開発スピードと柔軟性の向上に限界があります。アプリケーションの保守性や再利用性の向上、フロントとバックエンドの分離による高度な UI の実現、そして既に行っている社外への API 提供の高度化を進めていくには、次のステップである “クラウド ネイティブ化” に踏み出す必要があると判断しました」。
IaaS へのクラウド リフトを開始した際には、他社パブリック クラウドとの比較を行ったうえで Azure の採用を決めたと石原 氏。その理由は、以前からオープン系の基幹システムでは Windows サーバー上の .NET 開発を行っていたため、開発スキルをそのまま活かせ、かつコスト パフォーマンスが高いことだったと振り返ります。このような経緯もあり、クラウド ネイティブ化に踏み切る際にも、Azure の採用を前提に検討を行ったと言います。
コンテナ基盤の具体的な構築方法について検討を開始したのは 2022 年 1 月ごろ。Azure にはコンテナ基盤を構築するための複数の手段が用意されていますが、まずはこれらを机上で比較するところからスタートしました。そして 2022 年 3 月に、Azure Red Hat OpenShift の採用を仮決定したのです。

コンテナ基盤にデファクト スタンダードを採用し「次世代フロント基盤の新設」を宣言
Azure Red Hat OpenShift の採用理由について、明治安田生命 情報システム部 システム基盤開発室 システム基盤開発グループで主任スタッフを務める大内 章弘 氏は、次のように説明します。
「Red Hat OpenShift を採用したのは、他社の導入事例も多く、コンテナ基盤のデファクト スタンダードの一つだからです。IaaS 上に Red Hat OpenShift 環境を構築することも検討しましたが、マネージド サービスとして運用したいと考え、最終的に Azure Red Hat OpenShift に決めました」。
これに加えて「Azure Kubernetes Service (AKS) とも比較し、機能的な違いを評価しました」と言うのは、明治安田システム・テクノロジー株式会社からこのプロジェクトに参画している奥谷 陽子 氏です。「両者の大きな違いはバージョンアップのサイクルです。AKS よりもAzure Red Hat OpenShift は総合的なサポート期間が長めになっていました。当社にとってはサイクルが長いほうが運用しやすいと考えました。また GUI が充実しているのも、Azure Red Hat OpenShift の大きな魅力だと感じています」。
2022 年 4 月には、実際の環境を使用した PoC をスタート。「既に IaaS 上で稼働していたお客様専用サイト『MYほけんページ』のコードを使用し、アプリケーションの開発や移行が問題なく行えるかどうか、マイクロサービス化にあたりアプリケーションをどのように分割すべきかなどを、約半年かけて確認していきました」と大内 氏は語ります。
この PoC の後も、さらなる技術検証を行うと共に、DevOps の方法や開発者との役割分担の検討、先端の開発手法であるクラウド ネイティブ化についての社内プロモーションなどを実施。現在も稼働しているプライベート クラウド上のアプリケーションとの連携方法や、オブザーバビリティをどう実現するか、といった検討も進められていきました。2023 年 5 月には Azure Red Hat OpenShift の採用を正式決定しました。図に示す「次世代フロント基盤」構築プロジェクトを開始しました。
これは Azure Red Hat OpenShift を中心としたコンテナ基盤となっていますが、他にも Azure SQL Managed Instance や Azure Cosmos DB、Azure Cache for Redis、Azure Data Factory など、数多くの PaaS が利用されています。また、DevOps を実現するための CI/CD パイプラインには Azure DevOps Services を採用、自動ビルドとデプロイが行えるようになっています。
2023 年 8 月には、この基盤を活用したアプリケーション開発もスタート。2024 年 3 月には、既存アプリケーションの一部機能をマイクロサービス化したものがリリースされています。その後も順次、既存アプリケーションのマイクロサービス化が行われると共に、新規サービスの開発も並行して進められています。

CI/CD で開発とデプロイをスピードアップ、新規開発者の戦力化期間も短縮可能に
次世代フロント基盤は、開発/テスト用と本番用の 2 環境用意されており、リソースの払い出しやアプリケーションのデプロイを、開発者自身がセルフサービス型で行えるようになっています。石原 氏はこれによって、次のようなメリットがもたらされていると語ります。
「以前はリソースの払い出しやアプリケーションのデプロイをインフラ チームで行っており、開発者からインフラ チームへの依頼が必要でした。この基盤ではその必要がないため、開発とデプロイのスピードアップにつながっています」。
また、次世代フロント基盤はデファクト スタンダードなサービスを中心に構成したことで、従前の社内環境での開発に比べて、社外から新規開発者が参加する際に、この環境に慣れるまでの時間が短縮できる、という期待もあると言います。新規開発者を短期間で戦力化できれば、DX のさらなる加速が期待されています。
さらに、明治安田では .NET での開発に加えて Java での開発も行われており、それぞれの開発チームが同様の機能を重複開発するケースが少なくありませんでしたが、この問題を解決できる可能性も指摘されています。アプリケーション機能をマイクロサービスとして共通化することで、.NET 開発者と Java 開発者が同じモジュールを使うようになり、これがお互いの理解や連携を深めることにつながると考えられているのです。
なお、マイクロソフトをパートナーにすることで、充実したサポートが得られていることも高く評価されています。明治安田では IaaS へのクラウド リフトのころから「ユニファイド サポートの指定サポート エンジニアリング (DSE)」を利用していますが、クラウド ネイティブ化でもこのサポートが積極的に活用されています。
「クラウド ネイティブ環境の検討着手から現在まで、マイクロソフトにはさまざまな知見を提供していただきました。普段の定例会にも参加してくださっているため、問題が起こりそうな場合にも早く気付き、解決策もプロアクティブな形で提案してもらっています」 (奥谷 氏)。
明治安田では生成 AI への取り組みも進んでいますが、近い将来には次世代フロント基盤の上に、生成 AI アプリケーションの共通プラットフォームを構築することも検討されています。既に Azure OpenAI Service の環境を次世代フロント基盤上で動かすプロジェクトも計画されていると言います。
「GitHub Copilot も評価を始めており、今後はこれを活用した開発効率化にも取り組んでいきます」と石原 氏。「これからもアプリ開発チームと連携しながら、クラウド ネイティブ化による開発生産性向上とスピードアップに挑戦していたいと考えています」。

“クラウド ネイティブ環境の検討着手から現在まで、マイクロソフトにはさまざまな知見を提供していただきました。普段の定例会にも参加してくださっているため、問題が起こりそうな場合にも早く気付き、解決策もプロアクティブな形で提案してもらっています”
奥谷 陽子 氏: 基盤システム開発部 クラウド基盤開発室 新サービス基盤開発グループ グループリーダ ー明治安田システム・テクノロジー株式会社
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求




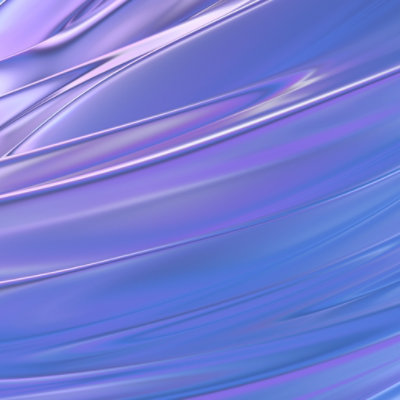

Microsoft をフォロー