長期化する新型コロナウィルス感染症による社会情勢の変化は、大学の運営にも大きな影響を及ぼしています。教職員や学生の健康を守り、安心安全かつ柔軟に大学を運営するためにはどうすればよいのでしょうか。
安全性と利便性の両立という課題を抱えていた創価大学が選んだのは、対象システムのログを収集し、アラート検出、調査、対処を自動で実施するサービス Microsoft Sentinel によるセキュリティの向上でした。
オンプレミス/クラウド混在のシステムも問題なく管理可能で、見えないリスクを可視化できる Microsoft Sentinel は、大学のセキュリティに関する業務を効率化するだけでなく、大学教職員の行動を過度に制限することのない環境づくりにも貢献しました。













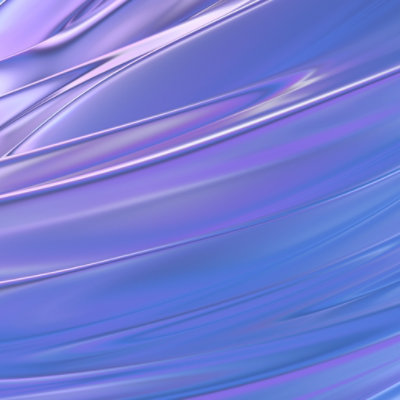




Microsoft をフォロー