いかに農業を持続可能な産業に進化させるか。農業 DX による「稼げる農業経営」の実現こそが、就農人口減少、後継者不足など様々な課題解決につながります。重要なポイントは、5 年先ではなく、デジタル技術で“いま”の農作業現場を改革し、“明日”を切り拓くこと。農業 DX 事業に取り組む株式会社Root は、AR (Augmented Reality:拡張現実)とスマートグラスを活用した農作業補助アプリケーションの実証実験を進めています。機械作業で必要となる「畑に直線を引くアナログ作業のデジタル化」はすでに実用段階に入りました。生産性・効率性の向上による人手不足解消、コスト削減へ、現場から始まる農業 DX。農業の未来が動き出しています。


農林水産省「戦略的スマート農業技術等
の開発・改良」プロジェクトに採択
農作業着に長靴、頭に HoloLens 2 を装着し、畑を見ながら空間に指でボタンを押す近未来的な風景。いま、農業は大きく変わろうとしています。埼玉県深谷市で、スマートグラス用農作業補助アプリケーション開発プロジェクト「Agri-AR」の実証実験が進行中です。Agri-AR は、農作業現場における単純作業の効率化を、AR (拡張現実)とスマートグラス技術を活用し、低価格で、誰でもどこでも使えるアプリケーションにより実現するものです。農業 DX 事業を手掛ける株式会社Rootが、深谷市とともに取り組んでいます。
Agri-AR では、AR を活用し実際の畑の風景に情報を付加して農作業を補助します。「2017 年に Root を創業した当時、Agri-AR は技術的観点から実現するのはまだまだ先という印象でしたが、マイクロソフトの MR デバイス HoloLens の登場により構想が現実的になりました」と、株式会社 Root 代表取締役 岸圭介氏は当時を振り返り、こう続けます。「2019 年から 2020 年にかけて HoloLens 用に基本的なアプリケーションを開発し農園でテストしました。その成果をもって深谷市 DEEP VALLEY agritech Award 2021 に応募したところ、最優秀賞の受賞とともに、深谷市から出資を受けて実証実験を行うプロジェクトに採択されました。そこから Agri-AR は動き出しましたね」
2022 年 4 月、Agri-AR に大きなターニングポイントが訪れました。農林水産省の令和 3 年度補正予算「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」プロジェクト(実施主体:生物系特定産業技術研究支援センター)に、同社の応募した「スマートグラス用 AR 農作業補助アプリケーション実用化のための研究開発」が採択課題として決定されたのです。深谷市の協力のもと農園に HoloLens 2 を無償で貸し出し、農作業現場で利用してもらうことで実用化に向けた改良を進めています。
農業 DX で使うなら「HoloLens 2」一択
農作業現場用 デバイス3 つのポイント
Agri-AR におけるアプリケーション開発は、他の農業ツール開発とは大きく異なります。開発を行う Root の岸氏自身が農業者として、自ら農作業を行う中でアプリケーションを開発。「現場で農作業をしていないと、生まれてこない発想ってありますよね。現場の課題は、現場にしかわかりません。農作業とアプリケーション開発を一体で捉えることができる点は、私の強みです」と岸氏は語り、こう強調します。「Agri-AR で使うデバイスは、HoloLens 2 の一択でした。現場の農業 DX を進めるデバイスの採用では、3 つのポイントを重視しました」

1 つ目は農作業しやすいハンズフリーであること。「タッチパッドで操作しなければならない他社スマートグラスに比べて、HoloLens 2 は空間でのボタン操作、音声認識などハンズフリーで操作できますよね。その点を高く評価しました」(岸氏)
2 つ目は振動にも強い、優れた装着感であること。「HoloLens 2 をかぶってトラクターに乗って作業しても全く違和感がありません。フィット感とともに、前後の重みのバランスがとれている感じがしますね」(岸氏)
3 つ目は高性能でアプリケーション開発環境が充実していること。「HoloLens 2 は、インターネット通信などスマートフォンと同じくらい基本性能が高い。また、マイクロソフトが提供するオープンソースでクロスプラットフォームの開発キット MRTK (Mixed Reality Toolkit)を使うと、アプリケーション開発時間を大幅に短縮できます。開発者として、マイクロソフトの MRTK は使ってみたい機能がまだまだ沢山あるツールですね」(岸氏)

Agri-AR に HoloLens 2 を採用して驚いたことがあると岸氏は話します。「HoloLens 2 は農作業現場で高齢者も含めてみんなが『使ってみたい』といいます。受け入れられやすさは、ずば抜けていますね。他の農業 DX プロジェクトでは、なかなかそうはいきません」
研究開発の 2 つのテーマがすでに実用レベル
将来の技術ではなく、すぐに使える技術を
「スマートグラス用 AR 農作業補助アプリケーション実用化のための研究開発」では、3 つのテーマがあります。「私自身が農作業中に思いついたテーマの中で、農園の収益力向上に直結するものを選びました」(岸氏)。
テーマの 1 つ目は AR 直線表示による農作業補助です。農作業では、耕運機など機械仕事を行う際に「直線を引く」工程が欠かせません。一般的に、2 人で両端から紐を引っ張り、中央まで歩いて足跡で線取りします。多くの手間と時間を要する作業です。「HoloLens 2 で数値設定をするだけで、実際の畑が映る画面上に仮想的にまっすぐな線が引かれます。かぶったまま線の上を歩くだけで線取りができるんですよ」(岸氏)
実証実験に参加している、深谷市の力丸農園の力丸敦夫氏は、「紐の場合、風があると線がまっすぐにひけないんですよね。ひとつ曲がるだけで全部に影響してしまいます。それが、HoloLens 2 をつけてアプリを起動するだけで、畑の中に直線が現れたときは『奇跡』だと思いました。風が強くても、画面上の線は曲がらないですしね。直線引き作業そのものをする必要がなくなるので、人件費を削減できますし、作業効率も上がります。HoloLens 2 の操作に慣れてきたので、あとは実践あるのみです」と力強く語ります。

テーマの 2 つ目は AR サイズ計測・判定です。作物の大きさは、商品価値、品質、収穫時期などに関わる重要な要素です。「当初は、画像認識技術を活用する予定でしたが、実証実験に参加している農園さんから、『指と指の間を測ればいいんですよ』というヒントをもらいました。それならマイクロソフトの開発キット MRTK ライブラリにある、指の位置を取得するハンドトラッキングが応用できることに気づいて、すぐに開発しました。左手と右手の区別もしてくれるので、両手の指を使えば 50 cmといった長いものも測れます。S / M / L / LL などサイズも自動判定し表示されるので、仕分け作業もしやすいですね」(岸氏)
学校、ホテルなどからケールをはじめとする 30 種類に及ぶイタリア野菜の受注生産を行っている力丸農園。すでに AR サイズ計測を活用していると力丸氏は語ります。「カーボロネロ(黒キャベツ)では、葉っぱを収穫するんですが、これまではあらかじめサイズを測っておいた棒をものさし代わりに使っていました。でも、慣れてしまうと作業者が直感で収穫してしまうので、品質にバラツキが生じてしまうんです。HoloLens 2 による AR サイズ計測なら、葉の厚みや長さを正確に計測できるし、ハンズフリーで収穫作業をしながら仕分けができるのがうれしいですね。いまは私しか使っていないのですが、近い将来にパートさんの作業支援にも利用したいと思っています」

3 つ目は最適ルートの算出とそのARガイドです。いかに農機の運転作業を効率的に行うか。ポイントとなるのが、最適ルートの選択です。問題は、土地の形状、広さ、作業タイプによって最適ルートが異なるという点です。「HoloLens 2 をつけて圃場(ほじょう)の周囲を歩くだけで、圃場(ほじょう)の形状と大きさを認識できる仕組みを開発中です。HoloLens 2 の環境把握機能と、GNSS (全球測位衛星システム)の精度の高い位置情報データを組み合わせることで実現できます。あとは、農機や作業タイプなどを入力して最適ルートをどう算出するかですが、その方法もわかっています。HoloLens 2 を利用したアプリケーション開発の可能性を再認識しましたね」
「これまではメジャーで圃場(ほじょう)の長さを測るのが常識でしたから、画期的ですよね」という力丸氏の言葉を受け、岸氏は「これからは HoloLens 2 の画面上で、線が何本引けて、作物をどのくらい植えることができるかが表示できますよ。いま、開発中です」と意気込みを語ります。
「将来の技術ではなく、すぐに使える技術という点が重要なんです。Agri-AR は、農業者の岸さんが現場目線で開発していることが大きなポイントだと思います。パソコンが苦手でも農作業はできますが、トラクターの運転は農作業には必須です。HoloLens 2 もトラクターと同じように実用的な技術として習得していきたいですね。1 つ 1 つの道具を揃えるのではなく、1 台の HoloLens 2 でアプリによって自分が使いたい機能を利用できる点も、農場によっていろいろな作業がある農作業現場に適しています」(力丸氏)
従来の農業に対するイメージ刷新を図る意義も大きいと力丸氏は強調します。「HoloLens 2 をかぶった姿は、すごくカッコイイですよね。表示されたボタンを押す音も未来感があります。農業体験に参加した子どもたちにも HoloLens 2 をつけてもらっています。子どもたちはもう夢中ですね。HoloLens 2 を使った観光農園ツアーも企画中です。これから農業は変わる。多くの人に関心をもってもらいたいですね」
Agri-AR で重視するポイントについて岸氏は語ります。「農作業を楽にするだけではなく、目的は農園の収益力向上です。Agri-AR を利用することで生産性向上、人手不足解消、コスト削減、品質向上など経営課題の解決につながる、“稼げる農業経営”の実現を目指しています」
現場からのアイデアを生かし機能を拡張
Agri-ARのレンタルサービス事業を構想
実証実験の成果について岸氏は話します。「いまは、20 台のHoloLens 2 を無償で貸し出しています。使ってもらうことで、現場から本当にいろいろなアイデアがあがってきますね。たとえば、肥料をまく道具を使う際に、『分速 25 メートルで歩くように』と仕様書に書かれているんですが、誰もわからない。すぐに、農作業中の歩行速度を AR 空間上で常に確認できるアプリケーションを開発しました。今後も、無償貸出の台数を増やして、どんどん農作業現場で使ってもらうことにより、機能を拡張し使いやすさもブラッシュアップしていきます。また、HoloLens 2 の利用で生じるデータの保存・活用において、Microsoft Azure などのクラウドとの連携も考えています」
最後に、今後について岸氏は言及します。「HoloLens 2 とアプリケーション、GNSS アンテナなどの機材をセットにしたレンタルサービスを構想中です。また、他のシェアリングビジネスとのコラボレーションも視野に入れています。実証実験で農園さんに貸し出す中で事業化の方向性を見極めたいと思います」
日々 Agri-AR の改良を重ねる岸氏。最新版では、MRTK ライブラリの音声認識技術を使って音声によるガイダンスコマンドを追加したといいます。「農作業は孤独なんです。でも Agri-AR を利用し始めてから楽しく作業ができるようになりました。こんなふうに音声があると農作業がもっと楽しくなりそうですね」と力丸氏は笑顔で語ります。HoloLens 2 の向こう側に農業の未来が広がっています。
※Agri-AR の実験内容・動画等の詳細は「Agri-AR 公式サイト」でご覧いただけます。
“「HoloLens 2 は農作業現場で高齢者も含めてみんなが『使ってみたい』と言います。受け入れられやすさは、ずば抜けていますね。」”
岸 圭介 氏, 代表取締役, 株式会社Root
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求




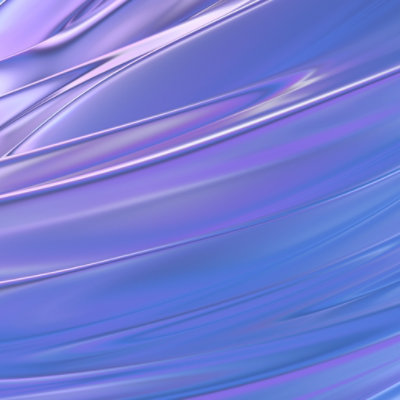

Microsoft をフォロー