高齢化、人口減少に伴い、我が国の医療業界においては介護ケアまで含めた医療システムの構築と医療の担い手の確保・育成が喫緊の課題となっています。特に大都市圏から離れた地方では高齢化、人口減少の影響が顕著であるうえに、交通や生活インフラの利便性が低いことから、地域内の医療機関の連携や人材の確保、医療環境の整備がより切実に求められています。
こうした課題に対応するために、全国の医療機関では ICT の活用による医療サービスや働き方の向上を進めています。愛媛県の社会医療法人石川記念会 HITO病院では、マイクロソフトの MR(複合現実)デバイス「Microsoft HoloLens 2」 を教育や研修、各診療科の診療サポート、さらには他の医療機関との連携に活用することで、人材育成の推進や医療サービスの維持・向上に役立てようとしています。














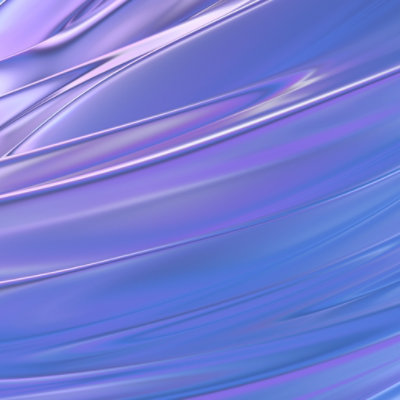




Microsoft をフォロー