2020 年の春から本格化した新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) への対応は、全国の地方自治体業務に大きな影響を与えました。日本で 5 番目に広い面積を誇る新潟県も、その例外ではありません。医療・教育・観光・各種産業など、あらゆる方面への支援が急がれる中、感染拡大防止の一環として、県庁の職員にもテレワークの実施が求められました。それは同時に、ICT 活用によって業務を効率化する「働き方改革」の重要性が増したことを意味しています。そして 2021年度、新潟県庁では「2 in 1 の端末であること」「閉域 SIM を利用できること」「ペン入力に対応していること」という 主な3 つの要件を提示して職員 5,700 名の業務用端末を調達。応札の結果、すべての条件を満たす端末として採用されたのが Surface Pro 7+ でした。


機動力の高い 2 in 1 のデバイスで、行政の DX を加速
2020 年から本格化した新型コロナウイルス感染症の拡大は、医療や教育をはじめ、観光事業や住民の生活を支えるエネルギー事情などに、多大な影響をもたらしました。各地方自治体は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して、さまざまな支援策を実施。新潟県においても、2020 年度に 482、2021 年度には 299 もの事業が実施されています。
この多くの事業の 1 つに、新潟県庁のテレワーク環境整備も含まれていると新潟県 知事政策局 ICT推進課行政デジタル化推進班 デジタル基盤担当 主任 吉武 翔 氏は説明します。
「職員のコロナ感染による業務停止を防止するため、テレワーク時に外部から庁内LAN を利用できる環境を整備するために、2021 年度に新しく職員分 5,700 台の PC 調達を行いました。しかし、この PC 調達は単純にテレワークに対応するためだけのものではありません。従来から推進してきた『働き方改革』ならびに『行政のデジタルトランスフォーメーション (DX) 』に、直接貢献する変革の 1 つになっています。」
新潟県庁が「働き方を変革するため」に必要とした端末の主な要件が下記の3点です。
- タブレットとしてもノート PC としても活用できる 2 in 1 の端末であること
- インターネットを介さず安全に通信できる閉域 SIM (別途調達済み) が利用できること
- 手書き入力用のペンを付属できること
吉武 氏は、上述の要件について次のように説明します。
「コロナ禍のためテレワークばかりに焦点が当たっていますが、庁内の『働き方そのものを変えるツール』として要件を定義しました。いつどこにでも携帯できて、安全に庁内 LAN に接続できる端末であることが重要でした。ペン入力に関しては、紙の書類を電子化したあとも『手書きで文字入力できるようにして欲しい』という要望があったものです。」
例えば、公共インフラ事業を管轄する部局の職員が現場に出て業務を行う場合でも、閉域 SIM を搭載した 2 in 1 の端末であればタブレットとして携帯して内蔵カメラで撮影し、その場で報告書を送信することが可能になります。2021 年度の調達において、新潟県がクラムシェル型のノート PC ではなく 2 in 1 の端末を指定した背景には「テレワークでの利用」のみならず、こうした “現場における活用シーン”を見据えた配慮が存在しています。
このように考えられた要件に加えて、コロナ禍の中で 5,700 台の発注に対応できる製品だったのが「Surface Pro 7+ でした」と知事政策局 ICT推進課行政デジタル化推進班 デジタル基盤担当 政策企画員 横山 大歩 氏は振り返ります。
「あの頃は世界各地でロックダウンしており、工場の製造ラインが止まっていました。半導体不足の影響が大きく、Surface 以外で私たちの需要に応えられる選択肢が存在していなかったようです。その点では、日本マイクロソフトの製品供給力に助けられました。」

総務部、知事政策局を中心に「デジ活」で庁内の意識変革をリード
新潟県 知事政策局 ICT推進課行政デジタル化推進班では、2021 年度末頃に Surface Pro 7+ の検収を終えると、総務部、知事政策局を中心に「デジタル活用推進キャンペーン」=通称 “デジ活” を展開。庁内のデジタル環境が整うことで、どのようなメリットが生じるのかという認知の拡大に努めました。その上で、多くの職員が初めて活用する 2 in 1 端末 (Surface Pro 7+) の操作方法を伝える少人数制の研修を1か月近く実施。2022 年 6 月から全庁での活用をスタートしています。
このデジ活は、2021 年 7 月に発足した「新潟県デジタル改革実行本部」が推進する行政の DX とも密接に連携しています。前述した Surface の使い方研修の参加者は、庁内の各部から任命された「DX 推進員」を中心に構成されており、彼らが各部における “教育係” を兼ねるような形式になっています。この点について同 ICT推進課行政デジタル化推進班 システム調整担当 主任 北林 王胤 氏は次のように説明します。
「まず、新潟県デジタル改革実行本部では『行政における DX』『暮らしにおける DX』『産業における DX』の 3 つの柱を掲げて、幅広い施策に取り組んでいます。その実行推進役として、知事政策局長を最高デジタル責任者とする『タスクフォース』が設置されており、各所属に 1 名ずつ任命された DX 推進員が各所属への技術支援を行うという体制を築いています。Surface の使い方説明に関しても、県庁の全職員に行うことは難しいので、DX 推進員を毎回 20 名ほど集めて細かく説明をして、各所属にそのノウハウを持ち帰ってもらうようにしました。」
こうした取り組みの成果もあり、Surface Pro 7+ の活用が開始されるとおおむね好意的に受け入れられたと吉武 氏は言います。
「庁内でアンケート調査を行った結果でも『会議や打合せに携帯できて便利』『ペーパーレス化に伴って書類整理や情報探索時間が短縮できた』『在宅勤務を行いやすくなった』など好意的な意見が多くありました。一部、従来使用していた 15 インチのノート PC よりも画面が小さいのは不便だという声もありましたが、携帯性の高さと、場所を選ばずに業務が行える利便性の高さが評価されています。」

豪雨・地震・鳥インフルエンザ。災害対策を迅速化
「閉域 SIM を利用できる 2 in 1 端末」が効力を発揮する場面がテレワークに限らないことは前述しましたが、特筆すべきは「災害対応」への備えにあると、吉武 氏は説明します。
「新潟県では過去に豪雨等による水害が度々発生しています。 2022 年も 6月から 8 月にかけて、何度も豪雨が発生していますし、今年 (2023 年) も 佐渡で記録的な集中豪雨が発生するなど、被害が続いています。こうした災害に対応する際に重要となるのが、避難されている住民の人数や物資の状況などの情報を、自治体側でスムーズに共有・把握することです。これまでは通信できるノート PC が非常に少なく、情報共有が非常に困難でした。しかし今は、多くの職員がどこからでも庁内 LAN に接続できる端末を利用しています。非常時だけ使用する端末ではなく、普段から使用している端末なので操作に戸惑うこともありません。タブレットとして利用すれば立ったままでも使えますし、災害への初動対応を少しでも早めることに貢献できていると思います。」
また、新潟県では2022年度に鳥インフルエンザの被害も多く発生しました。このような自然災害への対応においても、Surface Pro 7+ 活用を始めとする行政の DX によって業務の効率化と円滑化を図ることは、非常に大きな意味を持っているのです。
県議会・庁議のペーパーレス化と、準備の省力化
Surface Pro 7+ を携帯することで、庁内のペーパーレス化も大きく前進したと吉武 氏はいいます。
「従前は会議のたびに、紙資料を綴じた分厚いバインダーを持ち歩いていましたが、あれはとても重かったです。しかも、どれが該当する資料なのかを探すのが非常に大変でした。今は会議資料をファイルサーバーに格納して、リンクの URL をメールやチャットで共有するだけです。Surface Pro 7+ 1台を携帯するだけで大丈夫になりました。資料をプリントアウトする必要もないので会議の準備がとても楽になりました。」
Surface Pro 7+ の活用によってペーパーレス化が進んだのは、職員の会議だけではないと横山 氏は続けます。
「県議会・庁議も、紙資料の配布がなくなりました。今はもう完全にタブレットで資料を閲覧するスタイルに変わっています。従来、議会で配られる紙資料はかなりの量がありましたので、成果としては非常に大きなものがあると思います。」
また、知事政策局 ICT推進課においては「資料をプリントアウトする機会がほとんどなくなった」と吉武 氏は言います。
「今はメールだけでなくチャット ツールの活用も全庁で行われています。デジタルを通じたコミュニケーションが非常に充実したこともあり、資料をプリントアウトすることはほとんどなくなりました。私たち ICT 推進課に限って言えばペーパーレスはかなり進んだと言えると思います。ただし、県庁内には紙を必要とする業務は多々あり、部署ごとにペーパーレスの目標値も異なるでしょう。私たちの事例は、現時点においては例外的な数値であると言えると思います。」
Bing AI、自治体クラウド、ゼロトラスト セキュリティへの対応を見据えて
新潟県の DX は、まだ始まったばかりだと吉武 氏たちは声を揃えます。タスクチームでは、DX への取り組みを加速させるために、2023 年 4 月から DX 推進員の上司となる「DX 推進マネージャー」を各所属に任命。現場へのヒアリングを中心に行ってきた取り組みを加速させています。
「2021 年度からの取り組みを振り返った結果、DX 推進員自身が関与する業務における DX を検討することはできても、“所属全体” の働きを俯瞰して DX を考えることが難しいということが分かりました。そこで 2023 年度からは、所属全体を俯瞰できる上長を DX 推進マネージャーとすることで、より大きな気づきを得られるように体制を変えています。さらに DX の『トランスフォーメーション (変革)』という部分に意識を置き過ぎると、現場の方々に大袈裟に受け止められて、かえって腰が重くなってしまうのではないかという懸念もありました。そこで今はちょっとした業務改善も含めて、庁内にデジタル化の成功体験を積み重ねていこうという方針を立てています。」(北林 氏)
この「ちょっとした業務改善」に、Surface Pro 7+を導入したことが役立っていると、吉武 氏は言います。
「働き方を改革するならば、まず PC のように業務に不可欠なツールを変えることが重要と考えています。事実『2 in 1で閉域SIMを搭載できる端末』という私たちの要件を満たした Surface Pro 7+ は、業務の効率化・迅速化、そしてペーパーレス化に大きく貢献しています。チャット ツールの活用も、庁内のコミュニケーション・情報共有を円滑化することに大いに役立っています。また、テレワークに関しても申請自体を電子化して上長承認をスピード化したことで、コロナ禍が落ち着いた今でも『在宅勤務制度』そのものが利用しやすくなったという一面があります。私自身、子供が熱を出した際にすぐ在宅勤務に切り替えさせていただいたこともあり、こうした働き方の変化は、ツールによって目に見える変化が生じた結果だと言えるでしょう。」
しかし一方で「まだ変革すべき余地が大いにある」と吉武 氏は続けます。
「庁内業務にオープンなクラウドサービス、例えば Microsoft 365 のようなものを活用できるようになれば、さらに利便性が増すでしょう。庁内向け操作研修でMicrosoft OneNote を紹介したこともあり、スクラップブックのように活用している職員もいるのですが『情報をまとめやすくて、非常に便利』だという評判を聞いています。こうしたツールの活用が、もっと広く行えるようになれば、業務の改革もさらに進むと考えています。」
「業務を変革するために、新しいツールを活用する」という意味では、「すでに Bing AI の活用も始めている」と北林 氏は説明します。
「機密情報や個人情報などは入力しないなどのガイドラインをきちんと定めた上で、Bing AI の活用もスタートしています。所属によって使い道は様々あると思います。私の場合であれば、あいさつ文や礼状の作成であったり、県内の企業を紹介する文章の作成に役立てています。とても便利です。」
新潟県庁におけるデジタル環境の整備は、この先も続きます。中央省庁における「ガバメント クラウド」の取り組みも進んでいる今、自治体クラウドやオープンなクラウド サービスの活用、それに伴うゼロトラスト セキュリティの実現など、知事政策局 ICT推進課として対応するべき課題は数多くあると、横山 氏は声を強めます。
「ICT 技術の進歩に伴って、新潟県庁の働き方も今以上に変化していくでしょう。『行政の DX』『暮らしの DX』『産業の DX』という 3 本の柱を掲げて新潟県の DX が進んでいる今、知事政策局 ICT推進課として、常に最新の技術に関して情報を集め、検討を重ねていく必要があると強く実感しています。誤解のないように補足すると、私たちの目標は DX を達成することではありません。DX を推進する先には『県民へのサービスを向上させていく』という命題が常に存在しています。より良い行政の在り方に、少しでも貢献できるよう取り組みを続けていきたいと思います。」

“働き方を改革するならば、まずツールを変えることが重要です。事実「2 in 1で閉域SIMを搭載できる端末」という私たちの要件を満たした Surface Pro 7+ は、業務の効率化・迅速化、そしてペーパーレス化に大きく貢献しています。”
吉武 翔 氏, 知事政策局 ICT推進課 行政デジタル化推進班 デジタル基盤担当 主任, 新潟県
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求




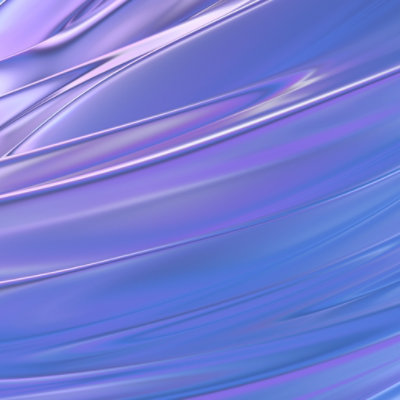

Microsoft をフォロー