『人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。』という「私たちの志」を掲げ、グループ全体でイノベーションを生み出す取り組みを推進している西日本旅客鉄道株式会社。ここではその一環として、デジタル ツールの活用と組織風土や文化の変革を推進する「Work Smile Project」が行われています。現場起点の業務変革のために、Microsoft Power Platform を活用した数多くの内製開発を実施。Power Platform の本格活用は 2022 年 7 月にスタートしましたが、それからわずか 1 年半でアプリ作成者数が 900 名、作成されたアプリ数も 1,200 本を突破しているのです。その一方で、事業の本丸である鉄道システムのイノベーションを推進する部署も、Power Platform と生成 AI を活用したアプリ「MIRAI」を開発。この組み合わせは「社員自らが業務を変革する」ための起爆剤になると評価されており、アイデア コンペの開催などを通じて、これらを活用したしくみが続々と生み出されています。


業務現場の課題の自己解決のため、アプリ内製ツールに Power Platform を採用
社会インフラを担う企業として、大きな転換期を迎えている社会の課題と真摯に向き合い、これまで以上にお客様視点で「つながりを進化させる」ことを目指している西日本旅客鉄道株式会社 (以下、JR西日本)。『人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。』という「私たちの志」を掲げ、グループ全体でイノベーションを生み出す取り組みを推進しています。その一環として行われているのが「Work Smile Project」です。
その背景や目的について「私たちが働く環境や行動は、2020 年から大きく変化しました」と語るのは、JR西日本 デジタルソリューション本部 DX人財開発室 (ワークデザイン) で課長代理を務める酒井 宏誌 氏。テレワークやスマート デバイス活用は当たり前のものになり、JR西日本グループも一丸となって、新しい働き方へのシフトを推進しているのだと言います。「そのために、業務変革を先導するエバンジェリストを鉄道の最前線で働く各職場を含め、全社で合計約 1,900 名選出し、自職場でのデジタル ツール活用推進や、日々の業務上の課題解決に取り組んでいます。これによって生み出される時間で新たな価値を創出し、その先にある “やりがい” につなげていこうとしています」。
そのためのツールとして重要な役割を担っているのが、Power Platform です。JR西日本では Microsoft 365 を 2021 年 10 月より本社部門より段階的に展開し、2022 年 7 月には全社的に展開しており、Power Platform の活用環境整備と試行運用については 2022 年 1 月に着手、Microsoft 365 の全社展開にあわせ、同年 7 月より本格活用を開始しています。
「当社が現場起点の業務変革ツールとして Power Platform を採用したのは、社内であたりまえのツールとして市民権があった Microsoft Excel / PowerPoint の知識・技術がある程度流用でき、Microsoft 製品全般と親和性が高いことを評価したからです。また、世の中に情報が多く、意欲ある社員が学習を進めやすい点も活用推進を後押ししています」 (酒井 氏)。
試行運用段階からさまざまなアプリケーションを現場主導で開発。その一例として挙げられたのが、広島土木技術センターが作成した「たちりす」です。
「これは、定例の保守点検作業や障害復旧作業の際に、指定された箇所の線路内に立ち入るための立ち入り箇所を確認するためのアプリケーションです」と説明するのは、JR西日本 デジタルソリューション本部 DX人財開発室 (ワークデザイン) の中司 桂一 氏。従来はベテラン社員や協力会社に聞き込みを行い、その場所を地図サイトなどで確認していましたが、管轄範囲が広くベテラン社員でもわからない場合があり、地図サイトでは線路の近くまで表示されないことも多く、立ち入りリスクが想定できないことも少なくなかったと言います。「これらの課題を解決するため、立ち入り箇所の地図や写真を収集し、アプリで確認できるようにしました」。

このようなアプリを現場社員自身が作り上げられる点が、Power Platform のインパクトであると中司 氏。「人口減に伴う労働者不足やベテラン社員の技術継承が当社全体で喫緊に迫っていた課題でしたが、広島土木技術センターの事例のように各現場起点でも解決に臨むことができるようになったのは大きな転換です。また同時に、アプリを作る体験、人が作ったアプリを利用する体験を通して IT リテラシーの大幅な向上が図れる点も、Power Platform を推進する中で感じている大きな強みです」。
この他にも、車両検査時の不具合の一覧を共有するために金沢支社の白山総合車両所が作成した「T-ima」などが、現場作業の効率化やリテラシー向上に貢献していると言います。
「500 名を超える社員が日々 Power Platform でアプリ作成や業務自動化を行っており、日常的に利用されているアプリ数は 450 本を超えています。業務が属人化することから会社として後押しできなかった会社非公認 Excel VBA マクロ職人が、Power Platform 市民開発者として日の当たる舞台で活躍できるようになりました」 (中司 氏)。
このような開発者を支援するためのコミュニティも、Microsoft Teams 上で運用されています。その参加者数も 1,300 名を突破。「相互扶助」「自分の躓きはだれかの躓き」「成果物はどんどん公開」という理念に基づき、「所属や肩書を越えてつながり、自分の強みや個性を活かす」場として、利用が浸透しつつあると酒井 氏は述べています。

鉄道システムのイノベーション部門でも Power Platform によるアプリ内製を推進
このような現場主導型の市民開発が進む一方で、事業の本丸である鉄道システム全体のイノベーションを推進する部署においても、Power Platform による内製開発が積極的に進められています。その一例が「MIRAI」というアプリケーションです。これは、券売機や改札機などの駅設備でトラブルが発生した際に、その原因や対応方法に関するナレッジから生成 AI が解決案を作成し、駅係員に提示するというものです。
「MIRAI 開発のきっかけになったのは 2023 年 6 月に、マイクロソフト主催の DX ユーザー会が行ったハッカソン イベントに参加したことでした」と語るのは、JR西日本 鉄道本部 イノベーション本部 鉄道システム室 業務革新 (企画) の藤村 勇斗 氏。ここで作成したアプリケーションが、MIRAI の原型になったのだと説明します。
「私は今まで駅係員や駅機械設備のコールセンター業務を経験したことがあるのですが、駅機械設備のトラブルへの対処は駅係員の経験に依存することが多く、すぐにトラブルの対処方法がわからない場合にはコールセンターに連絡する必要がありました。弊社の駅機械設備は約 340 種、約 46,000 台にも上り、このような多種多様な設備の専門知識を身に着ける事は駅係員だけでなく、コールセンター社員も非常に困難です。そこで、若手社員など経験が少ない人でも必要なナレッジがすぐに入手できるようなツールがあればいいと、以前から考えていました」。
そのために、生成 AI として Azure OpenAI Service、そのフロントエンドとしてPower Platformを採用。企画からわずか 1 か月弱で開発できたと藤村 氏は述べています。
「Power Platform は AI モデルを利用するうえで、スクラッチに比べて開発難易度や教育にかかるコストが低く、内製ですばやく PDCA を回すことが可能です」と言うのは、JR西日本 鉄道本部 イノベーション本部 鉄道システム室 業務革新 (開発) の松宮 寛 氏です。また、Work Smile Project では現場起点の業務変革が重視されていましたが、部門がアプリケーションを作成し、それを業務現場で使ってもらうという開発と利用のモデルでも、大きな効果を発揮できると指摘します。「全社員にアカウントが配備されている環境なので、最初に少数の現場で PoC を行い、その成果を基に改良版を他の現場を含む広範囲に展開することも容易です」と JR西日本 鉄道本部 イノベーション本部 鉄道システム室 業務革新 (企画) の堀 達広 氏は語ります。
2023 年 12 月には JR京橋駅での PoC を開始。これを翌年 2 月末まで実施し、駅で発生した機械故障に MIRAI を利用して対応されています。実際に MIRAI を使っている JR京橋駅の駅係員は次のように語っています。
「以前はコールセンターに電話をかけて情報を入手していましたが、MIRAI なら簡単なキーワードを入れるだけで対応方法を提案してくれるため、対応完了までの時間を大幅に短縮できるようになりました。これまで AI チャットはあまり使ったことがなかったので、新鮮な体験でした。また質問への回答と一緒に類似事象を提示してくれるのも助かります。新人しかいない時間帯でも、最初の対処をすばやく行えるようになりました」。
また JR京橋駅長の生田 氏は「欲張りかもしれませんが、駅設備のトラブル対応だけではもったいないと感じています」とも述べています。「このしくみは社員のレベルアップに大きな貢献を果たせるはずです。駅係員の仕事の本質は接客業なので、将来はそのノウハウも提案してもらえると助かります」。
実際に、JR京橋駅からコールセンターへの問い合わせ件数は、MIRAI の PoC 期間中、約 20% 削減されました。また駅係員へのアンケート調査でも、7 割が「これからも使いたい」という、ポジティブな回答だったと言います。
「MIRAI によって、社内に蓄積したナレッジを検索して生成 AI で洞察するという、1 つの型ができました」と松宮 氏。この「型」は、他の業務領域でも活かせるはずだと言います。「元々当社では、膨大なデータが蓄積されているものの、活用出来ていないという課題意識がありましたが、この型の活用により、2 ~ 3 日でプロトタイプを実装することができます」「自分自身で作ったアプリケーションで課題を解決するだけではなく、だれかが作ったアプリケーションを皆で活用するというのも、当社に適したスタイルだと感じています」。


生成 AI による働き方改革にも挑戦、前例主義や自前主義からの脱却も進む
生成 AI を用いた鉄道システムのイノベーションは「MIRAI」から始まっていますが、さらなるチャレンジも進めています。2023 年 10 月には「生成 AI による働き方改革への挑戦」と題したプレスリリースを発信。同時期に「生成 AI アイデア コンペ」や「AI-deathon」で社内のさまざまな部署から活用アイデアを募集しました。いくつかのアイデアは既に具現化され、PoC が実施されています。以下でご紹介するのはそのうちの 3 つのアイデアです。
- AI あるリスク提案くん
JR 電気部社員の施工打ち合わせの際に、過去の事例からリスクを抽出し、具体的なリスク検討をサポートする AI アプリ。 - 出夢 伊佐美 (いずむいさみ)
ISSM (イズム) という安全関連情報システムに蓄積された事故事例や対策の情報を活用し、作業の着工に向けた準備の際に、類似作業の労災情報を素早く・多く特定することで、作業安全管理をサポートする AI アプリ。 - LMS パートナー「とれいん」
人財育成の悩み相談や壁打ち、自分のキャリアや目標設定に関する相談ができる AI チャットボット。
「生成 AI と Power Platform の組み合わせによって、これまで活用しきれていなかった社内データの活用が容易になりました」と中司 氏。また「とれいん」では Microsoft Copilot Studio と Microsoft Dataverse が活用されており、これを将来は Microsoft Teams に組み込む予定になっていますが、幅広い選択肢の中から最適なツールを選べることも、マイクロソフト サービスの大きな魅力だと指摘します。「このような特長は、社員自らが業務を変革するための起爆剤になると考えています」。
その一方で堀 氏は「これまで鉄道会社は前例主義でしたが、今では新たなアクションを起こしやすい企業風土に変わりつつあり、これをデジタル ツールが後押ししているという実感があります」と言及。今はまだその過渡期ですが、5 ~ 10 年後には会社そのものが劇的に代わっているはずだと言います。「Power Platform とマイクロソフトの生成 AI はこのような取り組みに対して、ボトムアップとトップダウンの両方からアプローチできるツールであり、自前主義からの脱却や外部との共創にもつながると期待しています」。
最後に酒井 氏は「これまでの活動の推進にあたってマイクロソフトの皆様には、親身にサポートいただいています」と指摘。今後もマイクロソフトの生成 AI と Power Platform を活用し、業務現場を変革できるアプリケーションを数多く生み出していきたいと語ります。「マイクロソフトには一緒に変革を推進するパートナーとして、これからも継続的に支援していただきたいと考えています」。

“当社が現場起点の業務変革ツールとして Power Platform を採用したのは、社内であたりまえのツールとして市民権があった Microsoft Excel / Power Point の知識・技術がある程度流用でき、Microsoft 製品全般と親和性が高いことを評価したからです”
酒井 宏誌 氏, デジタルソリューション本部 DX人財開発室 (ワークデザイン) 課長代理, 西日本旅客鉄道株式会社
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求












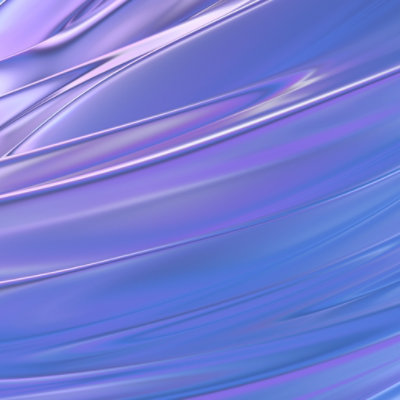

Microsoft をフォロー